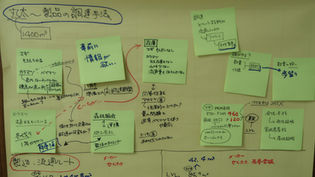宮城県林業技術総合センター設計ワークショップの主旨
このワークショップは、より良いCLT建築を実現する��ために情報・意見交換を行いながら、参加した技術者にCLT建築が実現するまでのプロセスを体験してもらうことや、県内技術者の技術レベルの向上を目的に開催されています。
多様なメンバーがアイディアや意見を持ち寄り、受託者と共に建物のデザインや構造、用途などを検討することで、より良いセンターを作り上げていきます。
これまでのワークショップと今後の予定
-
平成30年3月20日(火)に第1回ワークショップを開催しました。
-
平成30年4月4日(水)に第1回プレワークショップを開催しました。
-
平成30年4月24日(火)に第2回ワークショップを開催しました。
-
平成30年5月14日(月)に第2回プレワークショップを開催しました。
-
平成30年6月1日(金)に第3回ワークショップを開催しました。
-
平成30年6月6日(水)に第3回プレワークショップを開催いたしました。
-
平成30年6月29日(金)に第4回ワークショップを開催いたしました。
-
平成30年9月27日(木)に第5回ワークショップを開催いたしました。
-
令和元年12月23日(月)に第6回ワークショップを開催いたしました。
ワークショップの進め方
宮城県林業技術総合センター新築設計業務の概要
1.事業名称:林業技術総合センター新築設計業務委託
2.事業場所:黒川具大衡村大衡字はぬ木14地内
3.委託業者:(株)櫻田建築設計事務所
4.業務期間:平成30年2月14日から平成30年11月30日まで ※ただし平成30年7月までに基本設計を完了させる
5.業務概要:本館新築に係る基本設計及び実施設計業務一式 木造(CLT工法)2階 延べ面積1,235㎡
6.予定工事費:492百万円(直接事費ベース)
7.設計の基本コンセプト
(1)機能性や汎用性を重視し、研究施設としての用途に合致した施設とする。
(2)CLTパネル工法等新たな木材利用技術を積極的に導入し、シンボリックかつ普及性の高い工法を採用した研究
施設とする。
(3)災害に強く、安全性の高い施設とする。
(4)維持管理が容易で、リノベーションしやすい施設とする。
(5)地球環境、周辺環境に配慮した施設とする。
(6)先進的な機能の導入等による維持管理費の縮減を図った施設とする。
第6回ワークショップを開催しました(平成31年12月23日)
意匠設計、構造設計の成果報告会が行われました。これまでのワークショップを通して基本計画が進められ実施設計に至った経緯と、どのようにCLTを採用していくか、意匠設計担当の櫻田建築設計事務と構造設計担当のSA設計より報告されました。その後、3つのグループに分かれて「県産木材製品の具体的調達手法」のワークショップを行い、丸太から製品の調達や、製造・流通ルートについて検討しました。様々な分野のメンバーが集まって問題や検討事項の解決策を話し合いました。このような取り組みが、今後の木造建築の普及推進に繋がることを目指し、継続して意見交換を行っていきます。
櫻田設計事務所より、基本コンセプトについて報告がされました。CLTパネル工法など、新たな木材利用技術を積極的に導入し、シンボリックでかつ普及性の高い工法を採用した研究施設とするなど、どのような施設を目指すか報告されました。その後、3つのグループに分かれて設計ワークショップを行い県産材調達手法について話し合いました。CLT、LVL、集成材それぞれの調達方法に関して様々な制約はなしにして自由に検討し、課題や課題解決に向けたアイディアを出し合いました。
第5回ワークショップを開催しました(平成30年9月27日)
第4回ワークショップを開催しました(平成30年6月29日)
櫻田設計事務所より、これまでのワークショップで出されたアイディアをもとに設計された意匠案が提出
されました。工法については、普及性や技術者の育成など、今後のCLTの普及推進への貢献も踏まえて、CLTパネル工法ルート3での設計を進めるのが良いのではないかという意見が出されました。構造設計についてはのSA設計より事務所棟のCLTパネルの割付について報告がありました。
また、CLTの見せ方や、鉄骨の取り入れ方などのアイディアが出されました。魅力的な建物にするためにどのように鉄骨と組み合わせて、どう木を見せていくか、今後検討していくことになりました。
その他、材料供給側から材料調達の過程や納期について、防水・耐久性について等の報告もありました。
今後は分野ごとにそれぞれテーマを持ち寄って話し合いを進め、次回のワークショップで報告することになりました。
第3回プレワークショップを開催しました(平成30年6月6日)
櫻田設計事務所に、第3回ワークショップでのグループリーダー・サブリーダーを中心とするメンバーが集まり、ワークショップで出されたアイディアに基づき構造計画が検討されました。CLTパネル工法、在来軸組構法、RC造やS造とのハイブリッド構法、平面混構造・立面混構造など様々な可能性がでました。
2階建の事務・研究棟は、様々な用途の部屋があり、上下階の壁の位置を規則的に配置することがやや難しい平面計画です。2階の床をボックス構造の剛強な床にする案や、壁の配置を整理してCLTパネル工法ルート3の設計を目指す案などが出されました。
研修棟は、コア壁や強い柱で大屋根を支える大空間としてシンボリックな構造とする方向で概ね意見がまとまりました。大屋根にはCLT格子梁などの案が出されました。
この方針を受けて、構造設計担当のSA設計で構造計画を進め、次回第4回ワークショップで報告することになりました。CLTの特徴を活かした魅力的な構造計画となることが期待されます。
第4回ワークショップでは、内外装や仕上げ、木材生産などをテーマとする予定です。
第3回ワークショップを開催しました(平成30年6月1日)
第3回ワークショップは、構造計画の資料や大スパン屋根の架構、筋交い等の水平力負担部材の資料などが提出されました。4つのグループに分かれ、どのようにCLTを利用した構造形式が良いか議論しました。
シンボリックな研修棟、普及性の高い事務所棟にするために、CLTでボッスク状の箱を作り張り出す案や鉄骨とのハイブリッドにする案など、様々な提案が出されました。
これらの案を参考に6月6日に行われるプレワークショップで方向性をまとめ、構造形式が決まり次第、第5回ワークショップを開催する予定です。
グループに分かれた話し合いによって、たくさんの意見が出され、回を重ねるごとに大変充実したワークショップになっております。
第2回プレワークショップを開催しました(平成30年5月14日)
櫻田設計や各グループリーダー・サブリーダー、前田教授が参加しました。第2回ワークショップでの、3グループの議論や意見に基づいて、櫻田設計から、研修棟と事務・研究棟の2つの建物を配置する案が示されました。
① 研修棟は、CLTや木質構造を用いたシンボリックな建物
② 事務・研究棟は、CLTパネル工法や軸組み工法による普及型建物
という基本コンセプトが決まり、各部屋の配置や採用する構造形式などについて、様々な議論が交わされました。次回、6月1日の第3回ワークショップでは、構造形式を中心に議論をすることとなりました。
建物の形状も、ある程度具体的な形が決まりつつあり、この先の展開が楽しみです。構造は、純木造にこだわらず、RC造や鉄骨造などとのハイブリッド構造の提案もあり、魅力的な施設の実現に向けて進んでいます。
第2回ワークショップを開催しました(平成30年4月24日)
第2回ワークショップは参加者全員が意見やアイディアを出しやすいよう、3つのグループに分かれて話し合いを行い、最後に各グループのリーダーが意見を取りまとめ発表しました。
建物の設備や形だけでなく、建物周辺の環境や気候、その他さまざまな視点で意見やアイディアが活発に出されました。
また、建設のための問題解決をはじめ、発注者、使用者、建設者、一般利用者それぞれの立場からどのような建物が良いか、一般の市民も利用しやすい開かれた施設にするにはどのような設備があると良いかなど、さまざまな意見が出され大変有意義なワークショップとなりました。
第1回プレワークショップを開催しました(平成30年4月4日)
第1回ワークショップの開催を経て、櫻田建築設計事務所より建物の配置案が提出されました。
魅力的でシンボリックか��つ、普及性の高い建物をつくるために、どのようなデザインや構造がよいのか話し合いました。
また、職員だけでなく一般の方も学びや遊びの場として活用できる、展示ブースやショールーム、木育施設等の設置の他、屋外にアスレチック広場を併設したいなど多くのアイディアが出されました。
受託者、参加者が共に学べるワークショップとして今後は、見学会などの活動も検討しています。
第1回ワークショップを開催しました(平成30年4月20日)
平成30年3月20日に第1回ワークショップが開催され、40名を超える参加がありました。
ワークショップの主旨説明、事業の概要等の説明の他に、前田教授からCLT建築の事例紹介があり、ヨーロッパや高知で視察された建物をご紹介いただき、参加者はイメージを膨らませました。
設計をご担当される桜田建築設計事務所より、A~Cの3つの案が提出され、設計上の課題等をご紹介いただきました。
ざっくばらんかつ熱い議論が交わされ、エキサイティングなワークショップとなりました。
次回は4月24日(火)10:30~建設地である大衡の林業技術総合センターで開催することとなりました。